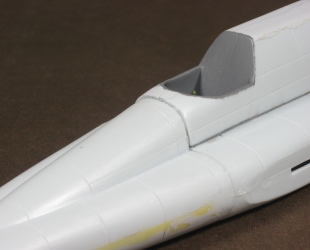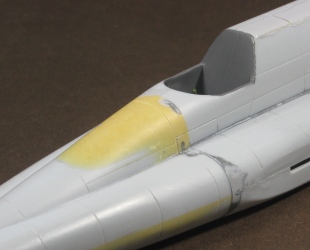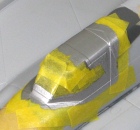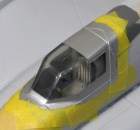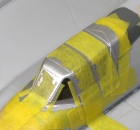| Il-40 改良試作型 制作記 |  |
|
| Amodel 1/72 |
| BOXアートの画像をクリックすると、「私が出会ったキットたち」の、それぞれのページへジャンプします。パーツ画像やデカールはそちらをご参照下さい。 このページに戻るにはブラウザの戻るボタンを使って下さい。 |
|
| ☆ ☆ ☆ 基本工作 ☆ ☆ ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ ☆ ☆ キャノピー と 小物 ☆ ☆ ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ☆ ☆ ☆ 基本塗装 ☆ ☆ ☆ | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ☆ ☆ ☆ 仕上げ塗装 ☆ ☆ ☆ | |||||||||||||
|
|||||||||||||